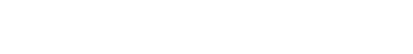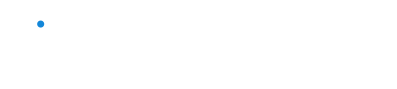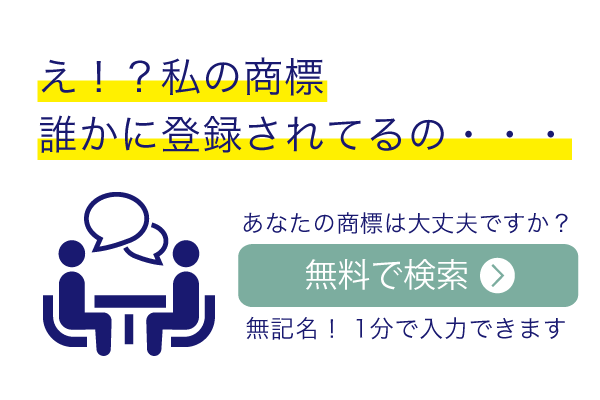商標用語辞典
商標登録で使用される専門用語を一覧でまとめています
あ行
特許出願や商標出願の審査において、審査官が引用した文献をいう。拒絶理由通知において示される。引例、引用例、引用特許、引用商標とも呼ばれる。
特許出願の審査においては、出願された発明に、新規性があるか、進歩性があるかなどが判断される。審査官は、新規性、進歩性が無いことを理由に出願を拒絶する場合、その根拠を示さなければならない。たとえば、新規性による拒絶を行う場合には、当該出願の発明と同じ発明が記載されており、当該出願の日より前に発行された文献を示すなどをして、拒絶理由の通知を行う必要がある。この文献が引用文献である。
”意見書”とは、特許出願や商標出願において、審査官の示した拒絶理由に対し、意見、反論を述べるために提出する書面をいう。拒絶理由通知発送の日から、指定された期間内(通常60日以内)に提出することができる。
審査官は、出願について審査を行い、特許(登録)すべきでないと判断した場合には、その理由を示して、出願人に意見を述べる機会を与えなければならない(特許法50条)。これを通知するのが、拒絶理由通知である。
拒絶理由通知を受けた出願人は、意見書を提出して、審査官の示した理由について反論を行うことができる。また、権利を請求する範囲を狭くするなどして、特許査定(登録査定)を得やすくするように、同時に手続補正書が提出されることが多い。
か行
”過失”とは、自分の行為から一定の結果が生じることの認識(予見可能性)があって、結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったことをいう。
損害の賠償を請求する場合、相手方の故意や過失によって損害を被ったことを立証しなければならない(民法709条)。しかし、特許権、意匠権、商標権が侵害された場合には、侵害者に過失があったものと推定される(特許法第103条等)。特許発明の内容は、特許公報によって公開されるため、無過失であることの立証責任を被告に転換したものである。
”過失の推定”とは、反証がない限り、過失があったものと判断することをいう。特許権、意匠権、商標権を侵害した者は過失があったものと推定される(特許法第103条、商標法第39条等)。
一般に不法行為に基づく損害賠償請求権は、侵害者が故意あるいは過失によって侵害行為を行った場合に認められる(民法第709条)。しかし、が侵害された場合には、侵害者に過失があったものと推定される。特許発明の内容については、特許公報、特許登録原簿等によって公示されているからである。したがって、事業として製品の製造や販売を行おうとする者は、当該製品が他人の特許等を侵害していないかどうかを調べておかなければならない。自らが開発した技術であっても、他人の特許権を侵害する場合もあり得るので注意が必要である。このような意味で、絶対的独占権といわれる。
一方、著作権法には、上記のような過失を推定する規定はない。したがって、独自に創作したものである限り、他人の著作権を侵害するおそれはない。このような意味で、著作権は、相対的独占権といわれる。
”間接侵害”とは、侵害の一歩手前の行為あるいは実質上侵害と同視しうる行為であり、特許権や商標権、著作権の侵害とみなされるものをいう(特許法第101条、商標法第37条、著作権法第113条)。
他人が特許発明に係る物(特許製品)を、無断で生産、販売等すると、特許権侵害となる。同様に、他人が特許発明に係る方法(特許方法)を使用すると、特許権侵害となる(直接侵害)。
これに対し、他人が特許製品の生産にのみ用いる物(専用部品)を生産、販売することや、特許方法の使用にのみ用いる物を生産、販売等することは、直接侵害に該当しない。しかし、これらの行為は、侵害に密接に結びついているので、特許権を侵害するものとみなされる(特許法101条1項)。また、その特許製品の本質的な部品であって、侵害に用いられることを知りながら、当該部品を、生産、販売等することも、特許権を侵害するものとみなされる(同101条2項)。
101条2項は、2002年の改正によって導入された概念である。プログラムを記録した記録媒体(CD−ROMなど)の販売行為などについて、装置特許にて権利行使を行う場合に、101条1項の間接侵害では十分な保護がなされないという問題があった(特許法によるソフトウエア保護の現状と課題を参照のこと)。寄与侵害の導入は、このような問題を解決するものとして期待されている。
他人が、無断で商品に登録商標を付けたり、その商品を販売すると、商標権侵害となる(直接侵害)。これに対し、他人が商品に付けるための登録商標のラベルを製造、所持したりする行為は、間接侵害として侵害とみなされる。
他人が、無断で著作物を複製すると著作権侵害となる(直接侵害)。これに対し、我が国の著作権の効力が及ばない外国で複製した著作物を輸入すること等が間接侵害として侵害とみなされる。
このような行為も侵害と同等に扱うことによって、特許権、商標権、著作権が十分に保護される。
”瑕疵”とは「きず」のことであり、法律上なんらかの欠陥があることを示す。
たとえば、本来、登録されるべきでなかった特許や商標が誤って登録されてしまったような場合、これらの権利は“瑕疵ある特許権”、“瑕疵ある商標権”ということになる。このような瑕疵ある権利に対しては、無効審判を請求して権利を無効にすることができる。
”慣用商標”とは、多くの企業が慣用的に使用したため、識別力を持たなくなった商標をいう。たとえば、清酒についての「正宗」は慣用商標である。慣用商標は、登録を受けることができない(商標法第3条1項2号)。
”拒絶査定”とは、審査の結果、審査官が出願を拒絶する場合に行う査定をいう(特許法第49条)。拒絶査定謄本を出願人に送達して行う。拒絶査定に不服がある場合には、拒絶査定謄本送達の日から30日以内に、拒絶査定不服審判を請求することができる。
なお、審査官は、拒絶査定を行う前に、拒絶の理由を通知して、出願人に意見の機会を与えなければならない(特許法第50条)。
”拒絶査定不服審判”とは、審査官の下した拒絶査定に対して不服を申し立てる審判をいう(特許法第121条)。3名または5名の審判官の合議によって、審査官の判断が正しいかどうかが審理される。
審理の結果、審査官の判断に誤りがあると考えられるときには、再度審査官に審査を命じるか、直ちに特許査定(登録査定)を行うかのいずれかが行われる。審査官の判断が正しいと思われるときは、拒絶査定が維持される。審判における最終的な決定を審決という。審決に不服がある場合には、訴訟を提起することができる(審決取消訴訟)。
審査において、審査官が登録できないと考えた場合、その理由を示す書面を出願人に送る。その理由を拒絶理由といい、この拒絶理由を書面により出願人に知らせることを拒絶理由通知という(特許法第50条)。
拒絶理由通知書には、何れの特許要件(登録要件)を満たしていないと審査官が考えているのかが示される。審査官は、いきなり最終的な拒絶(拒絶査定)を行うことはできず、まず、拒絶理由通知を行い、出願人に意見の機会を与えなければならない。
拒絶理由通知に対して、出願人は、補正書を提出して出願の内容を補正したり、意見書を提出して意見を述べたりすることができる。
”業として”とは、事業としての意味である。特許権侵害の成立要件であり(特許法第68条)、営利目的や反復継続性の有無を問わず、事業として特許発明を実施することをいう。つまり、特許製品を生産、使用したとしても、それが単に家庭的、個人的な実施にとどまる限り、特許権の侵害にはならない。
ヨーロッパで商標権を取る場合、各国ごとに出願を行ない商標登録することもできるが、EC全域に効力が及ぶ共同体商標(CTM:Community Trade Mark)を利用することもできる。
共同体の加盟国は、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イギリス、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ポルトガル、スペイン、スウェーデンの15カ国である。
共同体商標の制度は1996年4月1日からスタートしている。共同体商標の出願は、スペインのアリカンテにある共同体商標・意匠庁(OHIM:The Office for Harmonization in the International Market)が受け付けている。
共同体商標の出願があると、共同体商標・意匠庁は識別力などについて審査を行い、第三者から異議申立てを受け付けた上で審査をパスした商標を登録する。登録されるとEC全域に効力が及び、EC加盟国のいずれかの国で登録商標を使用していれば取消される心配はない。
ただし、EC加盟国のいずれかの国の不登録事由に該当するような商標は、審査段階で拒絶される。つまり、EC加盟国の全ての国の登録要件を満たすような商標でないと登録してもらうことはできない。登録されればEC全域に効力が及びメリットは大きいが、その分、審査段階で拒絶される危険性が高いということになる。
審査段階で拒絶された場合、その時点で出願を加盟国の国内出願に変更して各国ごとに審査を受けることができる。この場合は、不登録事由に該当しない国では登録してもらうことができる。しかし、共同体商標を国内出願に変更した場合、かえって費用と時間がかかることになってしまう。
したがって、確実に登録したい国には、初めからその国に対して通常の国内出願を行っておく方がよい。その上で、補助的に共同体商標の出願をしておくのが得策である。
“グッドウィル”とは、信用や商品・サービスの品質などから生じる顧客吸引力をいう。商品・サービスを通じて商標に化体される。商標の持つ商品識別機能、出所表示機能、品質保証機能、宣伝広告機能により、グッドウイルが蓄積される。周知・著名商標の方が、そうでない商標よりもグッドウイルは大きい。
”故意”とは、自分の行為から一定の結果が生じることを知りながら、あえてその行為をすることをいう。なお、結果発生が回避可能であるにもかかわらず、それを回避する行為をとらなかった場合には、”過失”となる。権利者から侵害警告を受けた後の侵害行為は、過失ではなく故意に行ったものとなる可能性が高い。
米国では、故意に特許権などを侵害した場合には、損害額の3倍の賠償を求められる場合がある。日本ではそのような法律上の規定はない。(弁理士 古谷栄男)
”工業所有権”とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の総称である。Industrial Propertyが”工業所有権”と翻訳されたものである。商標権を含んでいることから、狭義の工業だけでなく産業に関係した無体財産権というニュアンスであろう。最近は、工業所有権に代えて、産業財産権と呼ばれることも多い。工業所有権に、著作権などを加えたものの総称を、知的財産権(Intellectual Property)と呼ぶ。
さ行
”差止請求権”とは、自己の特許権、商標権、著作権などを侵害する者または侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止または予防を請求する権利である(特許法第100条、商標法第36条、著作権法第112条)。つまり、侵害者に対して、侵害品の製造・販売などを停止させたり(製造販売の差し止め)、侵害品を製造するための設備を廃棄させたり(廃棄除去請求権)することができる権利である。
この差止請求権を行使するに当たっては、侵害者の故意や過失を立証する必要がなく、権利者にとっては、侵害を排除するための最も効果的かつ直接的な措置である。
サービスマークとは役務(サービス)について使用する商標である。役務と商品は類似関係となり得ることが明らかにされており[商標法第2条第5項]、サービスの一環で使用した物でも、その形態によっては他の商品についての商標権を侵害するものとなり得る。
商標出願の際には、何れの商品(役務)についてその商標を使用するかを指定する。この指定された商品(役務)を指定商品(役務)という。
商標登録がされると、その商標を指定商品(役務)について独占して使用する権利が与えられる。また、他人が、指定商品(役務)に類似する商品(役務)について、類似する商標を使用することを禁止できる。なお、役務とは、いわゆるサービスのことである。
周知商標とは著名商標よりはやや知名度の低い商標であるが、その者の業務にかかる商品又は役務を表示するものとして需要者に広く認識された商標である。仮に商標として未登録であっても、他人の登録を阻止する効力がある[商標法第4条第10項]。外国周知商標と同一または類似な商標については不正競争目的が認められれば登録されない[商標法第4条第19項]。最近の審査基準では、国内未登録の外国周知商標を先取り出願したものや、出所表示機能の希釈化や名声を毀損させる目的で出願されたものは、不正競争目的であると推定される。
”出願人”とは、出願の願書において「出願人」の欄に記載される者のことをいう。
出願人は、「特許を受ける権利」を有している必要がある(特許法第49条6号)。この「特許を受ける権利」は、発明の完成と同時に発明者に原始的に帰属することになる。したがって、出願人には、発明者本人、あるいは、発明者から「特許を受ける権利」(特33条)を譲り受けた個人または法人がなることができる。
このように、発明者が「特許を受ける権利」を他人に譲渡した場合は、出願人と発明者とが別人になることになる。ただし、商標登録出願の場合は、発明者や創作者という概念はないため、そのような分離状態は生じない。
また、出願人は、権利能力(権利の主体になることができること)を有する者でなければならない。したがって、同好会などの法人でない団体は出願人にはなれない。
なお、米国では、出願人になれるのは発明者だけである。したがって、従業者発明の場合、多くは、発明者の取得した特許権を法人に譲渡する契約を交わすようにしている。最終的に特許権を取得する主体に着目して、米国では「譲受人(Assignee)」という表現が、日本での「出願人」に対応する言葉として用いられている。
商標権者が他人に登録商標の使用を認めるために設定、許諾するもので、専用使用権と通常使用権の2種類がある(商標法第30条、31条)。
専用使用権は商標権とほぼ同様の強力な独占的権利であり、設定後は商標権者自身も商標を使えなくなる。これに対して通常使用権はもう少し弱い権利で、商標権者に使用を許容してもらったにすぎず、独占的使用までは認められない。なお、通常使用権は専用使用権と異なり、かならずしも特許庁に登録する必要はない。
商号とは商人が営業活動上自己を表示するために使用する名称である。会社の場合、商号は設立登記の必要条件であり、漢字や仮名からなる文字列とされ、図形や色彩は構成要素とならない。
商号が登記されると、同一市町村内では同一や区別のつかない他人の商号登記は禁止される。
商号は登記によって不正競争目的についての挙証責任の転換の利益が得られる。商号権は商号専用権と商号使用権とからなり、その点で権利内容は商標権と似ている。
会社名は一般に商号であると考えられるが、同時にサービスや商品の出所表示機能を果たすことがあり、商号をそのままあるいは株式会社を除いた部分を商標登録することが多く行われている。
また商号である会社名が他人の登録商標に類似する場合には、その会社名には普通の態様で使用する限り登録商標の効力が及ばない[商標法第26条第1項]。
商標とは、文字、図形、記号もしくは立体的形状若しくはこれらの結合またはこれらと色彩との結合(すなわち標章)であって、その商品や役務(サービス) について業として使用されるものを言う[商標法第2条]。したがって、音声、におい、味(sensory mark)や動くマークは出所表示できるものであっても現行法上商標とならない。商標と言う言葉は、従来からの商品に付与されるものに限らず、サービスについて使用するサービスマークを含んでいる。
標章とは文字、図形、記号もしくは立体的形状若しくはこれらの結合またはこれらと色彩との結合である[商標法第2条]。
商標権とは、知的財産権のひとつで、自社の商品と他社の商品とを区別するための文字、図形、記号、色彩などの結合体を独占的に使用できる権利である。
特許庁に出願、登録することで、商標権として保護の対象となる。商品の販売や役務の提供を継続すると、使用されるブランドは需要者に広く知られることとなり、商品の品質や役務の質が一定以上のものであれば、業務上の信用力(ブランド)が化体し、財産的価値が備わるようになる。この財産的価値を保護するのに最も適切な権利が商標権である。商標権の存続期間は10年だが、更新も可能な永久権である。
商標を特許庁に登録する為には、まず、希望の商標を特許庁に出願する事から始まる。これを商標登録出願というが、略して商標出願と言ったり、一般の方は商標申請と使ったりもする。
実際は、出願の前に様々な調査をしなければ、登録の可能性を知ることは出来ない為、出願前には調査する事がほとんどである。
iRify国際特許事務所では、まずは同一商標があるかないかを調べる簡易な無料検索の「あるなし商標®検索」と、特許庁の本審査で行われる約30ある審査項目全てに対応した詳細な調査を行う「厳密商標調査」があります。後者の厳密商標調査により、登録の可能性、最善の登録方法、登録までの流れなど、専門家のアドバイスを受けることができるので、是非ご利用ください。
商標出願には、以下の手順が必要である。
1.商標登録にかかる出願書類の作成 登録を希望する商標、商標を付す商品・役務(サービス)、出願人名等を所定の書式に従い明記します。 2.商標登録出願(商標申請) 商標登録出願(商標申請)の手段は、以下の二つの方法がある。 特許庁へ商標登録出願書面の直接持ち込み、又は特許庁へ郵送による書面での出願(商標の出願審査費用を特許印紙にて支払う。この場合、電子化手数料が発生する。) インターネット出願ソフトを使用したオンラインによる出願(事前の特許庁への手続きが必要だが、電子化手数料が発生しない。) 商標登録出願で注意すべき事は、願書の作成である。願書は特許庁が指定した様式通りに作成しなければならない。願書に誤りがあれば特許庁から補正命令の知らせが入り(商標の記載がないなど致命的な誤りの場合は補完命令となり出願日の認定が送れる)、修正しなければならない。その分、商標登録の審査も遅れる為に審査結果も遅くなる。 出願にかかる国に支払う費用(特許印紙代という)は 3,400円 +(区分数× 8,600円) つまり、1区分12.000円。2区分は20.600円、3区分なら29.200円になる。 商標登録出願すると、先願権が与えられ(正しくは、商標登録を受ける権利)、2か月前後で特許庁の情報を受けた独立行政法人工業所有権情報研修館の運営するIPDL(特許電子図書館)に出願公開される。 商標登録出願から審査結果(査定)が下りるまでの期間は、約半年弱程かかる(指定商品や区分の数にもよる)。以前の審査期間は1年ほどかかっていたので、これでも待つ期間は短くなったのである。
1.商標登録にかかる出願書類の作成 登録を希望する商標、商標を付す商品・役務(サービス)、出願人名等を所定の書式に従い明記します。 2.商標登録出願(商標申請) 商標登録出願(商標申請)の手段は、以下の二つの方法がある。 特許庁へ商標登録出願書面の直接持ち込み、又は特許庁へ郵送による書面での出願(商標の出願審査費用を特許印紙にて支払う。この場合、電子化手数料が発生する。) インターネット出願ソフトを使用したオンラインによる出願(事前の特許庁への手続きが必要だが、電子化手数料が発生しない。) 商標登録出願で注意すべき事は、願書の作成である。願書は特許庁が指定した様式通りに作成しなければならない。願書に誤りがあれば特許庁から補正命令の知らせが入り(商標の記載がないなど致命的な誤りの場合は補完命令となり出願日の認定が送れる)、修正しなければならない。その分、商標登録の審査も遅れる為に審査結果も遅くなる。 出願にかかる国に支払う費用(特許印紙代という)は 3,400円 +(区分数× 8,600円) つまり、1区分12.000円。2区分は20.600円、3区分なら29.200円になる。 商標登録出願すると、先願権が与えられ(正しくは、商標登録を受ける権利)、2か月前後で特許庁の情報を受けた独立行政法人工業所有権情報研修館の運営するIPDL(特許電子図書館)に出願公開される。 商標登録出願から審査結果(査定)が下りるまでの期間は、約半年弱程かかる(指定商品や区分の数にもよる)。以前の審査期間は1年ほどかかっていたので、これでも待つ期間は短くなったのである。
商標登録を受けるために必要な要件。たとえば、商標の実体に関する要件と、出願書類の形式面に関する要件とがある。
商標の実体に関する要件としては、自他商品(サービス)識別力の有無や他人の先登録との類否などがある。商標登録要件を満足しない場合には、出願が拒絶される。
商標見本とは商標登録を受けようとする商標を表示した書面のことを言う[商標法第5条]。商標登録出願の願書に添付して出願される。実務上、同じ読み方のかな(カタカナ、ひらがな)表記と英字表記を2段にして商標見本を作成して出願することが行われており、それぞれ単に表記方法が違うだけで別出願にする必要はない。
”商標調査”とは、主に、他人の登録商標や出願商標を調査することをいう。
商標出願を行っても、同じ商標について既に他人が商標登録を受けていたり、出願をしていた場合には、登録を受けることができない。したがって、商標出願を行う前に商標調査を行うことにより、無駄な出願を排除することが好ましい。また、自社が使用しようとする商品名が、他社の登録商標である場合には、商標権を侵害することとなってしまう。その意味でも、商標調査は重要である。
2つの商標が類似するかどうかは、外観、称呼、観念の3つによって総合的に判断する。ただし、多くの場合、称呼(つまり読み方)が最も重要な判断基準となる。
また、2つの商品が類似するかどうかについては、特許庁が、その基準を公開している。
”商標の希釈化”とは、有名な商標(著名商標)について、他人がいろいろな商品やサービスに使用することにより、その著名商標の機能が弱められてしまうことをいう。特定の商品やサービスの商標として強く刻み込まれた消費者の認識が、他の商品やサービスに拡散されて、薄められることから希釈化(ダイリューション)と呼ばれる。
商標権者は、指定商品、指定サービスについて登録商標を使用する権利を専有し、その類似範囲(商品(サービス)または商標が類似する範囲)において他人が使用することを商標権侵害として禁止することができる。したがって、指定商品、指定サービスに類似しない商品やサービスに、他人が登録商標を使用しても、商標権の侵害とはならない。
しかしながら、著名商標については、指定商品、指定サービスと類似しない商品、サービスについて他人が使用した場合に、商標の希釈化が生じ、著名商標の所有者の利益を害するケースがある。そこで、このような希釈化行為は、不正競争行為であるとして、不正競争防止法により禁止されている。なお、商標登録されていない著名商標についても、希釈化の理論は適用される。
”商標登録表示”とは、その商標が登録されていることを示すための表示を言う。一般に、「登録商標」「商標登録第○○○○○号」「Registered Trademark」などの他、商標の右肩に(R)を付す場合も多い。
登録表示は法律上義務づけられているわけではなく、なるべく付すように努めるというように規定されている(商標法第73条)。
なお、登録されていない商標について商標登録表示を行うと、虚偽表示となって罪に問われる可能性があるので注意が必要である。
また、登録の有無に拘わらず、商標であることを明確にするため、商標の右肩にTMやSMを付す場合もあるが、これは登録表示ではない。TMはTrade Markの略、SMはService Markの略である。
商標権の内容は、こういう商標をこういう商品(またはサービス)に使う、という具合に決められている。この商品、サービスは第1類から第45類までの区分に分類され、整理されている。現在の区分は国際分類にしたがって分類されている。第1類から第34類までは商品についての区分、第35類から第45類まではサービスについての区分である。
1つの区分の中には実に多くの商品(またはサービス)が含まれている。そして、各区分の中の商品、サービスは、さらに複数の類似群というものに分けられている。この類似群は、商品、サービスについて、互いに類似する範囲を1グループにしたものであり、商標権の効力は類似群の範囲内にのみ及ぶ。
”審判”とは、審査官による最終処分等について、これが正当なものであったかどうかを、3名または5名の審判官の合議により審理を行うものである。拒絶査定に対する審判、無効審判、取消審判などがある。
審判を請求する場合には、特許庁に審判請求書を提出する。審判官の判断は、審決として出される。
商標の持つ本質的機能として、その商標により需要者が何人の業務に係る商品(サービス)であることを認識できる機能をいう。特別顕著性ともいう。
その商品(サービス)の普通名称のみからなる商標や、その商品(サービス)の機能の表示のみからなる商標は、自他商品識別力がなく、商標登録を受けることができない。同様に、慣用商標も登録を受けることができない。たとえば、コンピュータソフトウエアについての「ソフトウエア」や、ワープロソフトについての「文章作成」などは、普通名称であって自他商品識別力がなく登録を受けられない。
”実施権”とは、特許されている発明を実施するための権利をいう。いわゆるライセンスである。
実施権には、権利者とライセンスを受ける者との契約に基づく実施権と、権利者の意図とは関係なく法律上の条件を満たす者に与えられる実施権(法定実施権)とがある。
契約に基づく実施権には、”専用実施権””通常実施権”の2種類がある。”専用実施権”は、ライセンスを受けた者だけが独占的に実施できる(exclusive licence)。したがって、特許権者は、同じ内容について、複数人に専用実施権を設定することはできない。
また、設定した範囲内においては、特許権者であってもその発明を実施することはできない。専用実施権者は、設定を受けた範囲内においては、ほぼ、特許権者と同等の地位を有する。たとえば、設定を受けた範囲内において、侵害行為があった場合、専用実施権者は、差し止め請求、損害賠償請求を行うことができる。
なお、専用実施権は、特許庁の原簿に登録しなければ効力を生じない(特許法98条1項2号)。実務的には、ライセンス契約書において「独占的」である旨を、当事者間で定めておき、特許庁原簿への登録を行わない場合もある。このような場合、法的には、専用実施権と呼ぶことはできず、”独占的通常実施権”と呼ばれている。”独占的通常実施権”を有する者が、差し止め請求、損害賠償請求を行使できるか否かは、議論が分かれている。
”通常実施権”は、独占的ではなく単に実施するだけの権利である(non-exclusivelicence)。したがって、特許権者は、同じ内容について、複数人に通常実施権を設定することができる。
通常実施権者は、設定した範囲内において、他人が発明を実施した場合であっても、差し止め請求、損害賠償請求を行うことはできない。このような場合、特許権者に、差し止め請求、損害賠償請求を行ってもらうこととなる。
なお、通常実施権は、特許庁の原簿に登録しなくとも、当事者間の契約だけで効力を生じる。ただし、登録しておくことにより、第三者に対抗することができる(特許法99条1項)。たとえば、特許原簿に登録しておけば、特許権者がその特許を譲渡した場合でも、新しい特許権者に対し、通常実施権者としての地位を主張することができる。つまり、特許権者が変わっても、引き続き、特許発明の実施を続けることができる。
法定通常実施権には、特許権者が出願する前からその発明を実施していた者に法律上与えられる“先使用に基づく通常実施権”(79条)などがある。
なお、互いにライセンスしあうことを、クロスライセンスと呼ぶ。また、ライセンスを受けた者が、さらに他人にライセンスをすることをサブライセンス(再実施権)という。
”実施料”とは、特許されている発明などを実施させてもらうための対価をいう。いわゆるライセンス料である。製品1個につき、その価格の何%というように決められる。また、一括払いによる場合もある。
法律の適用範囲や効力範囲を、一定の領域内についてのみ認めようとすることをいう。たとえば、我国の特許法や商標法、著作権法が適用される領域は日本国内のみである。したがって、日本国の特許権に基づいて、米国での行為を日本国特許権の侵害として追求することはできない。米国での行為を追求したい場合には、米国においても特許権を取得する必要がある。ただし、著作権は、多くの国が出願という行為を要さずに権利を認めており、日本で著作権を有すれば他国でも同時に著作権を持つことになる場合がほとんどである。いずれにしても、属地主義のもとでは、各国ごとに権利が存在し、その効力も各国の法律によって定められる。
また、属地主義においては、どのような発明を特許として認めるか(特許要件)を、各国が独自に定めることとなる。したがって、同じ発明について、日本で特許されたにもかかわらず、米国で特許されないという事態もあり得る。
真正商品の並行輸入の問題などでは、属地主義との関係において問題が生じている。また、インターネット等の発達により、国境の概念が薄れ、属地主義に影響が生じる可能性も示唆されている。
”存続期間”とは、法によって定められた権利が存続する期間をいう。
主な権利の存続期間を下表に示す。
権利の発生 存続期間満了 備考
・特許権 設定登録 出願から20年 医薬品等について5年を限度とした延長あり
・実用新案権 設定登録 出願から6年
・意匠権 設定登録 設定登録から15年
・商標権 設定登録 設定登録から10年 何度でも更新可能(永久権)
・著作権 創作時 著作者の死後50年(法人著作は公表後50年)
・特許権などは、保護と利用のバランスを考慮して、無制限に独占権を認めるのではなく、一定の期間に限り独占権を認めるようにしている。ただし、商標権は、本来、同一の商標は同一の者が使用すべきであるという考えから、永久権としている。商標権者が不要であると考えた商標権については、10年ごとに整理するために存続期間を設けている。
”世界知的所有権機関”とは、全世界にわたって知的所有権の保護を促進し、パリ同盟やベルヌ同盟等の知的所有権関係の同盟間の行政的協力を確保することを目的として設立された国際機関である。World Intellectual Property Organizationの頭文字をとってWIPO(ワイポと読む)と略称される。
世界知的所有権機関は、世界知的所有権機関を設立する条約に基づいて設立されており、この条約には、全世界150カ国を超える国が加入している。
同じ発明について、2以上の出願があった場合、先に出願したものに権利を付与する主義をいう。先に発明したものに権利を与える先発明主義と対比される。出願日の先後が明確であるのに対し、発明日の先後の確定が困難であることから、先願主義の方が権利の安定性に優れている。日本を含め世界の多くの国は先願主義である。米国とフィリピンのみが先発明主義を採用している。なお、我が国は商標法もこの先願主義を採用している。
なお、先に出願をした方を先願、後に出願した方を後願といい、このような関係にあることを先後願関係という。
た行
団体商標とは事業者を構成員に有する団体がその構成員に共通に使用させる商標であり、団体の構成員が扱う商品・役務についての共通的性質を示すものである。登録可能な団体商標は公益社団法人や事業協同組合等であって、法人格を有するものである[商標法第7条]。財団法人、株式会社、フランチャイズチェーン、商工会議所は団体商標の登録を受けることができない。
著名商標とは日本国内で商品・役務の分野を問わず全国的に知られている商標である。従って、非類似の商品や役務に使用した場合でも、その出所を混同するような商標であって、防護標章登録による保護も可能である。仮に商標として未登録であっても、不正競争防止法などによる保護も得られる。著名商標については特許庁の電子図書館のサイトでの検索が可能である。
「手続補正書」とは、商標登録出願後に、出願内容を訂正するために提出する書面のことである。補正書には以下の2つの場合がある。
審査官や特許庁長官から補正指令や拒絶理由通知を受け取ってこれに対応して提出する補正。
出願内容の不備などに自ら気づいて自発的に提出する補正。
審査官による商標の審査が行われる前に、出願書類の形式的事項についての方式審査が行わる。方式的な不備(入力記載事項に誤りがあるなど)が見つかった場合には、上記の補正指令が出願人に通知される。これを受けた出願人は、指定された期間内に手続補正書を提出して、その形式的不備を解消しなければならない。手続補正をしなかった場合には、出願が無効とされるので注意が必要である。
実体的な審査においては、審査官から拒絶理由通知を受け取った後、この拒絶理由を解消するため権利範囲を減縮するために手続補正書を提出する場合が多くある。例えば、出願した商標と類似の先願商標があり、被っている商品・役務を諦めれば商標がとれる場合等には、意見書を作成するのではなく、補正書にて被っている部分を削除するという方法もある。
しかし、出願当初の範囲に記載した範囲を超えて補正することはできない。当初に記載していない事項を追加する補正を行うと、「要旨変更」であるとして拒絶されることになる。
つまり、補正書の内容の変更・削除は出来るが、追加は出来ないということ。
似た言葉に、「手数料補正書」という補正書もあるが、これは納付した手数料が正しくなかったときに、補正するために提出する補正書である。
尚、誤記であることが明確で、実質的に内容に影響を与えないような軽微な誤記の場合は、「職権訂正」として特許庁で訂正してくれる場合もある。
登録商標とは、商標法の定めに従って、特許庁に登録された商標のことである(商標法第2条第2項)。商標には、特定の商品やサービスなどを他と区別するために使用される文字以外にも、図形、記号、立体的形状などが含まれる。
商標登録する場合は、特許庁に商標登録出願を行ない、その商標をどのような商品やサービスに使うかを明示する。商標登録出願されると、特許庁で審査が行なわれる。この審査で登録査定がおり、登録料を納付すると商標が登録されて、登録商標となる。
商標登録されると商標権が与えられ、その登録商標を指定商品又は指定役務(サービス)に独占的に使うことができる(商標法第25条)。つまり、商標権は商品や役務に付ける「名前」や「ロゴマーク」を財産として守る、知的財産権である。
商標登録する場合は、特許庁に商標登録出願を行ない、その商標をどのような商品やサービスに使うかを明示する。商標登録出願されると、特許庁で審査が行なわれる。この審査で登録査定がおり、登録料を納付すると商標が登録されて、登録商標となる。
商標登録されると商標権が与えられ、その登録商標を指定商品又は指定役務(サービス)に独占的に使うことができる(商標法第25条)。つまり、商標権は商品や役務に付ける「名前」や「ロゴマーク」を財産として守る、知的財産権である。
ただし、商品・役務における商標権の効力範囲は、類似する商品・役務に限定されるので、他社が登録商標と全く同じ商標を使ってたとしても、指定商品又は指定役務と全く関係のないものに使っているのであれば、商標権侵害とは言えない。
®表示は登録商標について慣用されている表示であるが、表示の義務はない為、®表示がされていなくとも、商標権が存在しない(権利を主張できない)というわけではない。®表示の有無にかかわらず、商標権が存在する商標は事前承諾がなければ他人には使用は認められていないのである。登録された商標は、商標公報に以下の内容で掲載される(商標法第18条3項)。
商標権者の氏名・住所
商標登録出願番号及びその年月
願書に記載した商標
指定商品または指定役務
登録番号及び設定登録の年月日
その他必要な事項
登録異議申立とは、商標権付与後の登録異議申立制度であり、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に登録異議の申立をすることができる。利害関係のない何人でも請求することができる(商標法43条の2)。登録異議があった場合には、特許庁が自ら登録処分の適否を審理し、瑕疵ある場合にはその是正をする。
商標掲載公報の発行の日から2ヶ月を経過した後でも、無効審判を請求することができる。
異議申し立ての理由として、以下のものがあげられる。
商標登録の要件違反(商標法第3条)
不登録事由違反(商標法第4条第1項)
先願違反(商標法第8条第1項、第2項、第5項)
商標登録の取り消しの再登録禁止違反(商標法第15条第2項、第52条の2第2項、第53条第2項)
外国人の権利の享受違反(商標法第77条第3項において準用する特許法第25条)
条約違反(商標法第43条の2第2項)
商標登録を取り消す旨の決定をしようとするときは、商標権者等に対して取り消し理由を通知し、相当期間を指定して意見書の提出をする機会が与えられる(商標法43条の12)。
ちなみに平均審理期間は11ヶ月と公表されている。
登録査定とは、特許庁に出願処理をした出願商標が、特許庁の審査を経て審査官が商標を許可する場合に行う査定のことである。
商標出願を行った後、出願された商標は方式審査と実体審査において審査にかけられる。拒絶理由が特に無かった場合において、商標をすべきという審査官の最終判断が下りる。これが登録査定である。
提出書類の不備があり、これが解消された場合や、拒絶理由通知が出された後に、拒絶理由を解消した場合にも登録査定は下りる。
登録査定が下りただけでは商標は登録されていない。つまり、商標権はこの時点で発生しない。
登録査定が送付されて、30日以内に特許庁へ登録に必要となる費用(印紙代)を納付しなければ商標権の設定登録はなされない。ちなみに出願時に納付した印紙代とは別に収めなければならない。
登録料の納付を行わない場合には、その出願自体が却下処分になる。却下処分は取り消せないため、却下処分となった商標は、再度、出願から始めなければ商標登録することは出来ない。
登録料の金額は5年登録と10年登録で異なり、
5年登録の場合、1区分につき、21,900円
10年登録の場合、1区分につき、37,600円
を特許庁に収めることとなる。
区分数が増えるごとに5年登録であれば21,900円ずつ、10年登録であれば37,600円ずつ増額されていく。
取消審判とは、商標登録された商標をある一定の要件のもとで、登録商標を取り消すための審判を請求することができる制度である。
取消審判の種類
取消審判の種類は主に4つに分けることができる。 不正使用による商標登録取消審判
商標権の移転により混同を生じた場合における商標登録取消審判 代理人による無断登録における商標登録取消審判 取消審判の請求で一番多いのが不使用による商標登録取消審判である。 不使用による商標登録取消審判とは 取消審判とは、長期にわたって登録商標(出願をして、審査の結果、特許庁から商標登録をされた商標)を使用しない状態が続く場合に、何人でも(利害関係にない他人であっても)その指定商品(役務)にかかわる商標登録を取り消す審判を請求できる制度である。 ※この制度の目的は、登録商標を長期間に渡り使用していない状況では、第三者の商標採択の範囲を狭める可能性がある事、さらに使用によって商標に形成される業務上の信用を保護するという、本来商標制度に求められた趣旨に合致しない点などを踏まえ、不使用の登録商標を下記の要件のもとで取り消す審判が設けられたのである。 取消の要件
継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、各指定商品(役務)についての登録商標の使用をしていないときは、何人も(利害関係を要せず)、その指定商品にかかわる商標登録を取り消すことについて審判を請求することが出来る(商標法第50条第1項)。 しかし、例外として以下の場合には取り消されない。
取消審判の種類は主に4つに分けることができる。 不正使用による商標登録取消審判
商標権の移転により混同を生じた場合における商標登録取消審判 代理人による無断登録における商標登録取消審判 取消審判の請求で一番多いのが不使用による商標登録取消審判である。 不使用による商標登録取消審判とは 取消審判とは、長期にわたって登録商標(出願をして、審査の結果、特許庁から商標登録をされた商標)を使用しない状態が続く場合に、何人でも(利害関係にない他人であっても)その指定商品(役務)にかかわる商標登録を取り消す審判を請求できる制度である。 ※この制度の目的は、登録商標を長期間に渡り使用していない状況では、第三者の商標採択の範囲を狭める可能性がある事、さらに使用によって商標に形成される業務上の信用を保護するという、本来商標制度に求められた趣旨に合致しない点などを踏まえ、不使用の登録商標を下記の要件のもとで取り消す審判が設けられたのである。 取消の要件
継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、各指定商品(役務)についての登録商標の使用をしていないときは、何人も(利害関係を要せず)、その指定商品にかかわる商標登録を取り消すことについて審判を請求することが出来る(商標法第50条第1項)。 しかし、例外として以下の場合には取り消されない。
審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者もしくは、通常使用者のいずれかの者がその請求にかかわる指定商品(役務)のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明したとき。
商標権者が、他の人や企業に、使用する権利を与えていた場合、その使用権を持っている人や企業が使用していれば、不使用には当たらない。使用権の有無も確認する必要がある。
その指定商品について、その登録商標の使用をしていないことについて正当な理由がある場合、そのことを被請求人が明らかにしたき。
商標登録を取り消すべき旨の審決が確定すると、商標権は、当該審判の請求の登録の日にさかのぼって消滅したとみなされる。
は行
標準文字は特許庁長官の指定する書体の文字をあらわしたものであり、標準文字を使用することで商標登録出願の願書への商標見本の添付は不要になる。標準文字とは同一のポイント、横書きの一段の文字列である。色彩のあるもの、2段書きのもの、草書体や特殊なフォントの文字や、縦書きの文字、図形や図形を含むものは標準文字による商標登録出願ができない。
”普通名称”とは、その商品またはサービスの一般的な名称であると認識されるに至った名称をいう。たとえば、「りんご」や「アップル」は、食物としての「りんご」に関する普通名称である。このような普通名称を普通に用いたものは、商標登録を受けることができない(商標法3条1項1号)。ただし、コンピュータという商品について、「アップル」という名称は、普通名称ではないので、登録を受けうる。
”普通名称”とは、その商品またはサービスの一般的な名称であると認識されるに至った名称をいう。たとえば、「りんご」や「アップル」は、食物としての「りんご」に関する普通名称である。このような普通名称を普通に用いたものは、商標登録を受けることができない(商標法3条1項1号)。ただし、コンピュータという商品について、「アップル」という名称は、普通名称ではないので、登録を受けうる。
特許出願や商標出願の審査において、審査官が引用した文献をいう。拒絶理由通知において示される。引例、引用例、引用特許、引用商標とも呼ばれる。
特許出願の審査においては、出願された発明に、新規性があるか、進歩性があるかなどが判断される。審査官は、新規性、進歩性が無いことを理由に出願を拒絶する場合、その根拠を示さなければならない。たとえば、新規性による拒絶を行う場合には、当該出願の発明と同じ発明が記載されており、当該出願の日より前に発行された文献を示すなどをして、拒絶理由の通知を行う必要がある。この文献が、引用文献である。
ま行
本来、登録されるべきでなかった特許や商標を無効にするため、特許庁に請求する審判である(特許法第123条、商標法第46条)。無効理由はそれぞれの法律に定められており(特許法であれば、新規性や進歩性等がないこと)、無効審判を請求すると特許庁の審判官が裁判のような厳正な審理を行う。そして、無効にすべきであるとする審決(無効審決)が確定した場合は、通常、権利は初めからなかったものとみなされる。なお、無効審決に不服がある場合には、審決取消訴訟を提起することができる。
ら行
平成9年4月1日から法律が改正され、立体的な商標も特許庁に登録できるようになっている。これまでの商標登録は、文字や記号、図形等に限られていた。すなわち、紙の上に書けるような文字やマークしかしか商標登録できなかった。立体商標も商標登録できるようになったことで、たとえば飲食店のカニの立体看板も商標登録できるようになった。
また、このような看板としての立体物の他、たとえば飲料水のビンの形状も立体商標として商標登録することが可能である。ただし、もともと商標は、特徴的なものしか登録されないため、従来からあるようなありふれた形状のビンは商標登録できない。工夫をこらした、特徴的な形状のビンであれば登録の対象となる。
その他
(R)マーク
®マークとは、Registered Trademark(登録商標)を意味します。
®マークは、米国の連邦商標法上で規定されたものであり、米国商標法では、商標の損害賠償を請求するためには®マークをつけることが条件として規定されております。一方、日本においては、登録商標に®マークをつけることは義務づけられていません(商標法73条)。ただ、「登録○○号商標」等の表示をすることが努力義務として定められております。しかし、「登録第○○号商標」と書いてしまうと、すごく堅すぎる、と思われる方もいるでしょう。そのような場合には、登録商標には、®マークを付するとよいでしょう。 他人が無断で使用することを防止する効果があると考えられます。尚、商標が出願中などで登録されていないにもかかわらず®マーク表示をすると、虚偽表示として、懲役又は罰金に処される可能性があるのでご注意ください。
(R)マークの付け方など、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
TMマークとは、Trademarkの略語であって、単に「商標」を意味するに過ぎません。よって、登録していない商標、例えば、出願前の商標や、出願中の商標についてもTMマークを付することができます。
TMマークの付け方など、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
©マークとは、copyrightの略です。
著作権に関する国際条約は2つあり、(C)マークはその一つの万国著作権条約にあたります。万国著作権条約のみに加入している国は、(C)マークの表示が方式要件を満足したものとの意味があり、表示しないと著作権を主張できません。しかし、日本のようにもう一つの国際条約であるベルヌ条約に加入し、無法式主義を採用していれば、一切の手続き・記載が発生せずとも著作権が発生します。よって、日本において、著作物には(C)マークを表示せずとも創作した瞬間から著作権が発生することになります。
(C)マークの正しい書き方は、「© 著作権者 最初の公開年(後に更新年) 」であり、順番が違っても問題はありません。尚、「Copyright」や「All Rights Reserved.」の記述は、(C)マークの意味を知らない人向けの補足説明であり、法的な意味はありません。「Copyright」は著作権、「All Rights Reserved」は、全ての権利を保有するということを意味します。